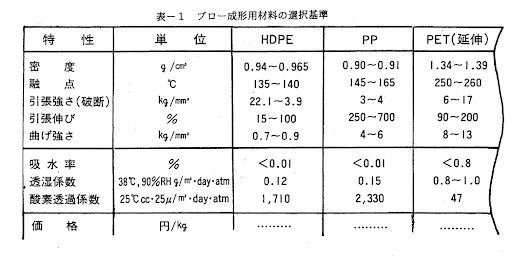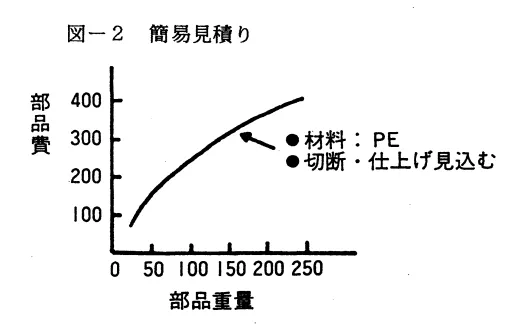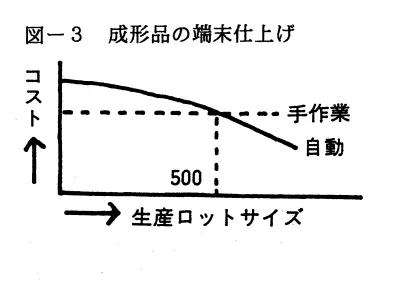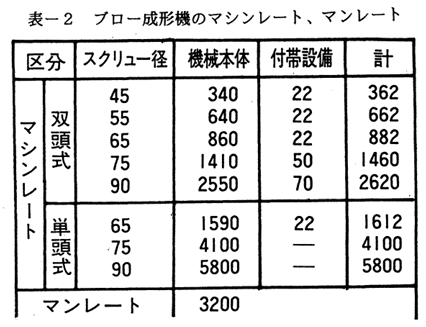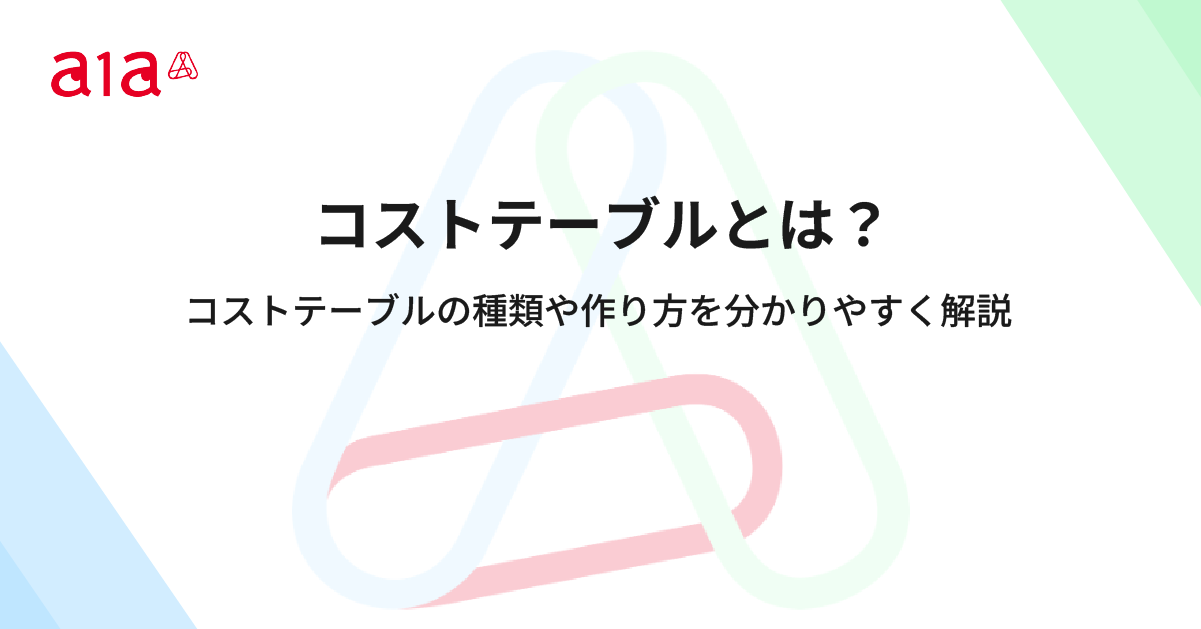
投稿者プロフィール
- A1Aブログは製造業向け調達データプラットフォーム「UPCYCLE」を提供するA1A株式会社が運営するメディアです。製造業の調達購買業務に役立つ情報を発信しています。
最新の投稿
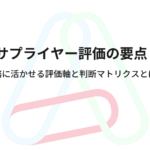 2026年2月2日サプライヤー評価の要点―実務に活かせる評価軸と判断マトリクスとは
2026年2月2日サプライヤー評価の要点―実務に活かせる評価軸と判断マトリクスとは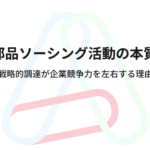 2025年12月26日自動車部品ソーシング活動の本質と進化― 戦略的調達が企業競争力を左右する理由
2025年12月26日自動車部品ソーシング活動の本質と進化― 戦略的調達が企業競争力を左右する理由 2025年12月2日4M変更とは?不具合品流出を防ぐためのマネジメント手法を解説
2025年12月2日4M変更とは?不具合品流出を防ぐためのマネジメント手法を解説 2025年11月17日グリーン調達の使命:自動車EVシフトによる調達部門への影響を解説
2025年11月17日グリーン調達の使命:自動車EVシフトによる調達部門への影響を解説